ライブのチケット販売ページでよく見かける「注釈付き指定席」。
初めて見ると「これって当たりなの?ハズレなの?」と迷ってしまいますよね。
注釈付き指定席とは、ステージ演出や機材などの関係で「一部が見えづらい可能性がある席」として販売されるチケットのことです。
公式側としては「全部がしっかり見えるとは限りませんよ」という注意書きをつけたうえで、通常より少し安く販売されることが多いのが特徴です。
しかし、実際には「思ったより見えた!」「むしろ近くて最高だった!」という声も多く、ライブファンの間では“穴場席”として人気になることも。
では、そんな注釈付き指定席の実態とは?ここから詳しく解説していきます。
注釈付き指定席とは?

イブやコンサートのチケットでよく見かける「注釈付き指定席」は、ステージの構造や機材の関係で一部の演出が見えにくくなる可能性がある席のことです。
とはいえ「全く見えない座席」ではなく、角度や位置によってはむしろステージに近くて神席になることもある“穴場ポジション”。
通常より安く販売される場合もあるため、「多少の見切れより熱量重視!」というファンに人気の選択肢です。
注釈付き指定席の基本情報
注釈付き指定席は、多くの場合ステージの真横・斜め後ろ・機材の近くなどに設置されます。
ステージ正面から見ると一部演出が見えなかったり、メインスクリーンが隠れてしまう可能性があります。
ただし「全部見えない」わけではなく、角度次第ではアーティスト本人が一番近くに来る距離になることも。
特に花道やバックステージに立つ演出が多いアーティストのライブでは、むしろ正面席より激近になることもあるんです。
また、公式が「注釈付き」として販売しているだけで、実際はそこまで支障がないケースも多いのが実情。
特にドームやアリーナ規模の会場では構造によって見え方が違うため、運次第で当たり席にもハズレ席にもなりうるというのが注釈席の面白さと言えます。
通常指定席との違い
通常指定席は「ステージ全体が見えることを前提」に販売されるため、視界に関するリスクは少なめです。
一方で注釈付き指定席は「少しでも見えづらい可能性がある」席をまとめて販売しているため、公式としてはクレームを避けるためにもこの表記をつけています。
とはいえ、価格が通常より安く設定されていたり、一般販売後に追加で出されることも多く、「とにかく現地に行きたい!」というファンには狙い目。
また、通常席に落選してしまった人にとっては「復活チャンス」になることも多く、実際に申し込むファンも多いのが特徴です。
一言で言えば、「多少のリスクはあるが、思わぬ当たり席に化ける可能性もある席」というのが注釈付き指定席の本質です。
注釈付き指定席の魅力
注釈付き指定席の一番の魅力は、「近さ」と「価格」です。
正面の良席は高倍率で当たりにくいですが、注釈付き席はライバルが少ない分、当たりやすい傾向があります。
また、アーティストによってはステージ横を頻繁に通る演出があったり、スクリーン越しではなくナマの表情が見える距離になることも。
「正面の全体演出をしっかり見るか」「近さを優先して臨場感を楽しむか」──その選択肢を得られるのが注釈付き指定席の最大の魅力です。
注釈付き指定席の見え方

注釈付き指定席といっても、場所によって見え方は大きく変わります。
実際に多くのファンの声を参考にしながら、シチュエーション別の見え方を詳しく見ていきましょう。
サイド席とメイン席の視界の違い
サイド席はステージを横から見る形になるため、真正面からの演出は見えづらくなる場合があります。
特に大型スクリーンやレーザー演出は角度によって視界が制限されることも。
しかし、ステージ上のアーティストが近いのは圧倒的にサイド席です。
一方で、メイン席(やや後方や斜め位置)は全体を俯瞰しやすく、演出も比較的見やすい傾向があります。
つまり、「近さ重視ならサイド」「全体把握ならメイン寄り」と考えると分かりやすいでしょう。
どちらにしても、注釈付き指定席=「見えない席」と決めつけるのはもったいないのです。
角度や倍率による体感の変化
ライブの見え方は「席の位置」だけでなく、双眼鏡(オペラグラス)の倍率によっても大きく変わります。
5倍〜8倍程度の双眼鏡があれば、たとえステージが斜めでも表情までしっかり確認できます。
逆に言えば、双眼鏡なしだと「顔は見えるけど表情までは分からない」という席もあるので、注釈席に挑むなら双眼鏡は必須装備と考えておいたほうが安心です。
また、角度によっては照明が眩しく感じることもあるので、サイド席に慣れていない人はサングラスや帽子で調整するのもおすすめです。
演出や機材が与える影響
注釈付き指定席の視界を左右する大きな要因が演出と機材配置です。
特に大型LEDスクリーンやスピーカー、照明の支柱などが前にあると、部分的に見えなくなることがあります。
とはいえ最近のコンサート運営はかなり配慮されており、”完全に見えない席”を販売することは稀です。
機材が邪魔になると言っても、「立てば見える」「体を左右に傾ければ見える」という程度が多め。
逆に、機材の裏側に立ったスタッフの動きや、ステージ裏の様子が見えるという「レアな体験」をできるのも注釈席ならではの魅力です。
注釈付き指定席のメリット

ここでは、注釈付き指定席をあえて選ぶ人が多い理由を紹介します。
価格に対する価値とは?
注釈付き指定席は通常価格よりも数千円安く設定される場合が多いです。
それにもかかわらず、実際の見え方が通常席と大きく変わらないことも多く、コストパフォーマンスの高さが魅力です。
もちろん「演出の一部が見切れる可能性」というリスクはありますが、それを理解した上で申し込むなら「安く現地参戦できる」という大きなメリットになります。
ファンのための特別な体験
注釈付き指定席には、通常席では味わえない「距離の近さ」「レアな目線」「裏側の動き」などの特別な楽しみがあります。
ステージ真横からアーティストを見るのは、ある意味でテレビやDVDでも味わえないアングル。
ファンサービスが多いアーティストなら、横をチラッと見ただけで目が合うことも…!?なんて声もあります。
「正面からじゃなくても、近くに感じたい」──そんなファン心に寄り添う席でもあるのです。
公演ごとのチェックポイント
注釈付き指定席を選ぶなら、過去のライブ構成を調べるのがポイントです。
- 花道やバックステージが多いアーティスト→注釈席が神席になる可能性大
- 正面演出重視のアーティスト→サイド席だとやや物足りない可能性
SNSやチケット掲示板などで「●●ツアーの注釈席はどんな感じだった?」という情報を調べる習慣をつけておくと失敗しづらくなります。
デメリットと注意点

もちろん、注釈付き指定席にもデメリットはあります。
ここでは申し込む前にチェックしておきたい注意点を整理しておきましょう。
見切れ席との関係
よくある疑問が「注釈付き指定席と見切れ席の違いって何?」というもの。
- 注釈付き=「一部が見えづらい可能性あり」
- 見切れ席=「明確に見えない部分があります」
というニュアンスの違いがあります。
つまり注釈付きは「薄いリスク」、見切れ席は「確実に視界制限あり」という認識でOKです。
ただし表記は主催者によってバラバラなので、申し込む前に「どこが見えないのか」をしっかり確認することが大切です。
座席位置による制限
注釈付き指定席は座席によって満足度が大きく変わります。
たとえば、ステージ真横の一列目なら超神席ですが、角度がつきすぎると首が痛くなることも。
また、バルコニー席や上段席の場合は、柵や手すりが視界に入ることもあります。
「座席の高さ」「支柱の有無」「スクリーンの位置」など、可能であれば座席図や過去のレポを確認しておきましょう。
会場ごとの特徴
同じ「注釈付き」でも、会場の構造によって見え方は全く異なります。
- ドーム → スケールが大きく、多少の見切れでも演出が派手なので楽しめる
- ホール → 視界が狭くなるとかなり見えづらいことも
- アリーナ → 花道があるタイプなら注釈席が激近になる可能性大
会場の「形状」と「ステージ構成」が噛み合うかどうかが満足度を大きく左右します。
実際の感想と体験談
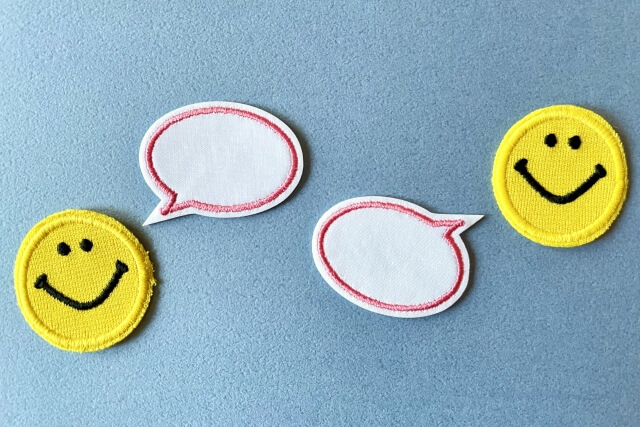
ここからは実際に注釈付き指定席に座った人のリアルな声を紹介していきます。
ファンからの具体的な反応
- 「ステージが半分くらいしか見えなかったけど、推しが近くに来た瞬間すべて報われた」
- 「機材が邪魔だったけど、そのおかげでスタッフさんと仲良くなれた(笑)」
- 「正面席より断然テンション上がった。横から見るダンス、めちゃくちゃカッコイイ!」
など、ポジティブな声も多く見られます。
もちろん「やっぱりスクリーンが見たかった」という声もあるので、「演出をしっかり楽しみたい人」より「距離感を重視する人」に向いている席と言えるでしょう。
公演ごとの違い
同じアーティストでも、ライブツアーによって注釈席の満足度は大きく変わります。
例えば、
- 花道がL字型→サイド席が超当たり席に
- ステージがフルフロント型→見切れが大きくなりがち
など、構成によって印象は全く違います。
過去のライブ映像や参加者レポを参考にしながら「今回はサイド強い!」と判断できるかどうかが成功の秘訣です。
アーティストの演出との相性
注釈付き指定席が向いているのは、「客席へのファンサが多いタイプのアーティスト」です。
ステージ中央で踊るだけの演出より、花道やムービングステージを使うタイプのライブの方が満足度が高い傾向があります。
逆に、演劇調や映像重視の演出の場合は、少し物足りなさを感じる可能性もあるので注意しましょう。
注釈付き指定席の販売情報

注釈付き指定席を狙うなら、いつ・どこで・どのタイミングで申し込むかが重要です。
購入タイミングを見極める
注釈付き指定席は多くの場合、通常チケットの抽選後や一般販売の後に「追加枠」として販売されます。
これにより、通常チケットで外れた人にも再チャンスが巡ってきます。
また、公演直前に「機材席解放」や「当日引換券」として販売されることもあるため、公式サイトやファンクラブのメールをこまめにチェックしておくのが鉄則です。
人気の会場や公演を確認
注釈付き指定席が販売されやすいのは、ドーム・アリーナ規模の大規模会場です。
特に東京ドーム・京セラドーム・さいたまスーパーアリーナなどは例年注釈席が出される傾向があります。
一方、小規模ホール公演ではそもそも注釈付き席が出ないこともあるので、公演ごとの傾向を事前に把握しておくと安心です。
チケットの倍率と競争状況
「注釈付きなら倍率低そう」と思われがちですが、人気アーティストの場合はむしろ注釈席の方が倍率が高くなることもあります。
「どこでもいいから入れればOK」というファンが多いほどこの傾向は強まります。
確実に狙うなら、一次抽選で通常席・二次で注釈席という戦略的な申し込みもおすすめです。
まとめ
注釈付き指定席は、ただの「見えづらい席」ではありません。
ステージとの距離が近くなる可能性を秘めた“チャンス席”でもあるのです。
確かに、演出の一部が見えなかったり、スクリーンが隠れてしまうこともあります。
でも、その代わりに推しがすぐ目の前に来る瞬間や、通常席では味わえないアングルでライブを楽しめることもあります。
ライブにおいて一番大事なのは「完璧な視界」よりも、自分自身がどれだけその空間を楽しめるかです。
「多少のリスクがあっても、現地に行きたい」「近さを優先したい」「レアな席を体験してみたい」──そんな気持ちがあるなら、注釈付き指定席は間違いなく挑戦する価値のある選択肢です。
一度そのスリリングな視界でのライブを経験すれば、きっとあなたもこう思うはず。
「正面だけが正解じゃない」と!







